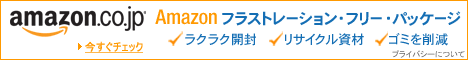壊れた心をどう治すか コフート心理学入門Ⅱ(PHP新書)和田秀樹

私が、Kindle本を耳読した本の感想を、ご紹介しています。 本選びの参考になれば、と思っています。
読み終えるまでの平均的な時間(3時間24分)
感想…
コフート心理学入門Ⅰを読んだときにも共感したのですが、心理学をかじったものにとっては、非常に分かりやすい内容でした。境界性パーソナリティや自己愛についての記述は、何度も読みたくなり、Kindle Unlimitedではなく購入したくなりました。2度読みましたが、わかりやすいのでもう少し深めてみたくなっています。もちろん、耳読なんですが。
コフートの心理学は、本当に日本人向けだと感じています。
商品説明
米国の精神分析の世界で人気を集めているというコフート心理学。本書は、日本におけるコフート心理学研究の第一人者である著者が、『<自己愛>と<依存>の精神分析』に続くコフート入門書の第2弾として著した1冊である。コフートの人物像や理論、その背景にある人間観などに焦点を当てた前作に対して、今回はコフートが米国の精神分析学や医学の歴史的文脈のなかでどのような位置づけにあるのかに着目し、現代におけるその理論の有効性を探り出している。
書き起こしは精神分析の祖・フロイトからで、それに続くアンナ・フロイト、メラニー・クライン、カーンバーグ、マーガレット・マーラーらによる精神分析理論のモデル・チェンジの過程を順にたどっている。著者はそこで「ボーダーライン」「自己愛」「パーソナリティ障害」「自己」といった概念がどうとらえられているかを読み解くほか、治療のアプローチや患者層の違いなどにも目を向ける。
なかでもコフートについては、「自己の構造」がバラバラな状態、つまり「中核自己」が父母との対象関係においてしっかりと形成できなかった状態を精神の病理ととらえたこと、依存関係や共感を通じてその患者の「心の健康」を目指したことなどを読み解く。このコフート理論こそ、自己形成を行う家族環境が変わった現代人に、また「甘え」の文化をもち、心の中を解剖するような従来の精神分析を好まない日本人に合っているのではないか、と説く。
だれにでも起こりうる心の問題を想定した著者の精神分析論はじつにわかりやすい。現代日本の心をめぐる課題も見えてくる。(棚上 勉) --このテキストは、絶版本またはこのタイトルには設定されていない版型に関連付けられています。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
juneberry-miyatomo.hatenablog.com